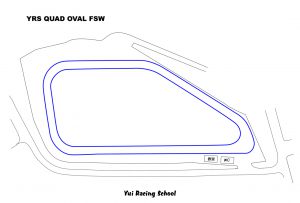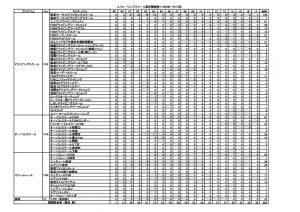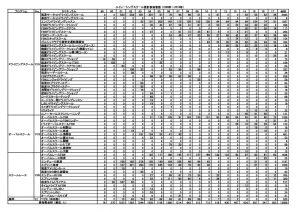昨年12月。ユイレーシングスクール20周年記念にアルピーヌA110の体験試乗を行った。大好評だった。自分のクルマと比較することで、それまで見えなかった自分の運転の本質と、自分のクルマの特性が見えてくる。今回は第2弾としてFJ1600を体験してもらう機会を準備した。FJ1600は既にレースを終えているカテゴリーではあるけれど、マシン自体は多数現存するし、写真を見てもらえば入門用フォーミュラカーと言っても上級フォーミュラと変わらない手法で作られていることがわかる。そのFJ1600に乗ってもらおうという企画だ。
細部をよく見てほしい。ノーズダイブもせずテールスクワットもしないで平行移動するがごとく走るフォーミュラカーの作りがわかる。ノンパワーでダイレクト感に圧倒されるステアリングとブレーキ。当日晴れならば、温まるほどにグリップが増しステアリングが重くなるスリックタイヤを履いた本格的なレーシングマシンに乗ることができる(雨天の場合は溝付きレインタイヤ)。
FJ1600を安全に走らせるためと楽しんでもらうために、ご自身のクルマでブレーキングとイーブンスロットルの練習をしてから試乗していただくことになるが、9月3日(木)に開催するYRSドライビングスクール筑波を受講しながらFJ1600ライドに挑戦してみてはいかがだろう。
・ 9月3日(木)開催 YRSドライビングスクール筑波 開催案内
・ 9月3日(木)開催 YRS FJ1600ライド開催案内

東京R&Dが制作したFV95のフロントサスペンション
プッシュロッド式インボードサスペンション
コイルダンパーユニットがシャーシ側についているので
ばね下重量を低減できて路面追随性を高めている

同じくFV95のフロントサスペンション
バンプステアを避けるため
ステアリングタイロッドとアッパーアームが同じ高さにあるのがわかる

同じくFV95のフロントサスペンション
ステアリングラック、アンチロールバーが見える

同じくFV95のフロントサスペンション
ベルクランクを使ったプッシュロッド式インボードサスペンション

FV95のリアサスペンション
同じくプッシュロッド式インボードサスペンション

同じくFV95のリアサスペンション
コイルユニットの下にスバル製トランスミッションが見える

FJ1600に共通のパワープラント
スバルEA71型エンジンとトランスミッション
パワーは約110馬力
ドライバー込で465Kgのマシンを走らせるには十分

FV95のドライビングポジション
シートは固定式
試乗時にはバスマットでドライビングポジションを調整する

WEST04Jのフロントサスペンション
上下Aアームのダブルウィッシュボーンサスペンション
プッシュロッド式インボードサスペンション
Aアームがワイドスパンなのに注目

WEST04Jのリアサスペンション
上下Aアームのダブルウィッシュボーンサスペンション
プッシュロッド式インボードサスペンション
ロアにトルクロッドが追加されている

同じくWEST04Jのリアサスペンション
コイルユニットが内蔵されているので空力的にも有利

WEST04Jのリアエンド
元はFF用だったエンジントランスミッションユニットをミッドシップに移植
長いが剛性のあるリンクでスバル製トランスミッションを動かす

WEST04Jのエアファンネル
奥に見える赤いのが給油口
安全燃料タンクはドライバーズシートとエンジンの間にある

WEST04Jのダッシュボード
初期にはアナログ式メーターが並んでいたが
全盛期にはマルチファンクションのデジタルメーターに

WEST04Jのドライビングポジション
FV95よりスペースがある
FJ1600のコクピットは狭いのでクイックリリースステアリングハブが標準装備(写真はWEST04J)
WEST04Jのエンジンをかけてみる(バーグラフ式のデジタルタコメーターは映せなかった)