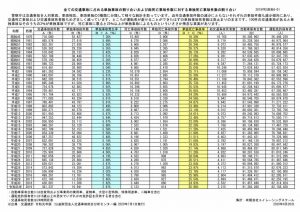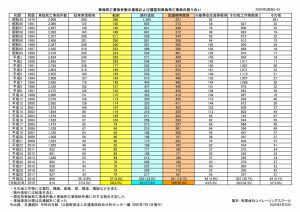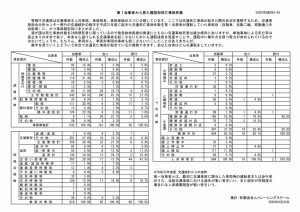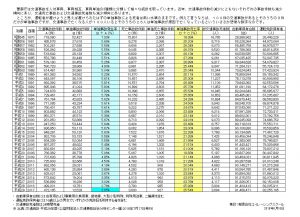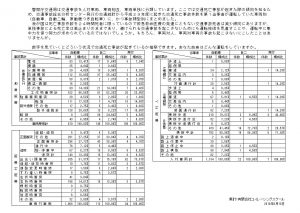ルノーのブログでブレーキペダルをかかとを上げて踏むことに疑問をなげかけてから、ユイレーシングスクールの卒業生もメールを送ってくれるので紹介します。
実は、お恥ずかしいことにかかとを上げてブレーキペダルを踏まなければならない理由について、思慮が足りなかったようです。いくつかのケースがあるようですが、ハイヒールを履いた女性の場合がそのようです。ただ弁解するわけではありませんが、無視していたわけではなく、50年前に免許を取った免許人口の少ない時代を過ごしてきたものとしては、ハイヒールでは運転しにくいのだから運転用の靴をクルマの中に用意するというのが常識でした。少なくともボクのまわりにはハイヒールのまま運転する人はいませんでした。
いつのころからか、安全に運転するという意識が薄れてきているように思います。免許人口が増えるのと比例して運転に対する意識の平均値が下がったのでしょうか。それともクルマが安全になったせいで人間の安全意識が薄れたのでしょうか。つっかけやサンダルで堂々と大型トラックから降りてくる職業運転手にも、『お前、プロなんだろ』と毒づきたくなること多数です。
横道にそれましたが、KさんとOさんのメールです。
——————————————————————————————————————————————
8月のスクールは無理ですがツーデーには参加するつもりで予定を組んでいます。
さてブレーキペダルとかかとの話題がありましたが、別の角度からみたこんな記事が
Yahooに載っていました。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190821-00168208-kurumans-bus_all
しかし女性がかかとを床につけたがらないのは、体格の問題だけではなく、女性用の
靴はハイヒールではなくてもかかとがかなり高いものが多く、かえって不安定になる
可能性があること、また靴の後ろを傷つける可能性があって、おしゃれで高価な靴
だったりすると嫌がることもあると思います。
また運転教則本ではかかとを離して踏み替えるよう指導されていますが、これは教本
の普通免許対象が乗用車に限らずマイクロバスから軽トラック、小型特殊までを対象
にしていて、床からペダルが生えているような種類のものでも通用する非常に普遍的
なペダルの踏み方を念頭に入れているためだと思います。教本が常に正しくて最適と
いうことにはなりません。
こんにちは、ルーテシア&バルケッタのKです。
ブレーキの踏み方に関する件ですが、ヤフーニュースの記事で面白いのを見つけましたので、お知らせします。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190821-00168208-kurumans-bus_all
この記事で特に面白いなと感じたのは、日産「デイズ」開発についての下記の部分です。
> デイズの開発現場では、カカトを床に付けずにブレーキを踏む女性が多いことを男性の開発者に話すととても驚かれたといいますが、社内の女性たちの声を集めるなどしてなんとか男性陣に理解してもらったそうです。
> そしてデイズでは、カカトを床につけずにブレーキを踏んでも、初期制動がなるべく穏やかになるよう、また恐怖感を感じずに着実に減速できるよう、何度も試行錯誤しながらブレーキフィーリングを煮詰めていったほか、足の小さな人でもしっかり踏めるように、ブレーキペダルの角度を研究して採用したとのことでした。
実際に運転したことが無いので分かりませんが、どんなフィーリングになっているのか少し興味あります。(笑)
以下、記事の全文もコピーしておきます。
ーーーーーーーーーーーーーーー ここから ーーーーーーーーーーーーーーー
「ブレーキの踏み方に男女差がある!? なぜ女性はカカトを付けずにペダルを踏むのか?」
クルマの運転の仕方は個人差があるといいますが、とくにブレーキペダルの踏み方は大きな差があります。なかでも女性のブレーキの踏み方は、男性にとっては信じがたい動作でおこなっているといいますが、それはどんなことなのでしょうか。
女性好みの装備や機能だけでなく、運転姿勢に着目してクルマを開発
アクセルペダルを踏む、ブレーキペダルを踏む、ハンドルを動かすという3つの操作は、クルマを運転する上でもっとも基本となる操作です。
男性には理解しがたい!? 女性の使い勝手を考慮した日産「デイズ」を画像でチェック(27枚)
女性はカカトを床に付けずにブレーキを踏む人が多い
そうはいうものの、クルマの操作方法は、すべてのドライバーが同じようにおこなっているとはいえず、年代や性別、体格の差などによってバラつきがあることがわかっています。
なかでも、もっとも大きな違いが見受けられるのがブレーキペダルの踏み方です。男女でブレーキの踏み方が違うというのですが、どのように異なるのでしょうか。
昨今は、女性の意見を反映させるために、新型車の開発チームで女性の評価担当者が活躍することが増えてきました。
運転が不安な女性や初心者でも運転しやすいクルマを目指したダイハツ「ミラトコット」や日産「デイズ」では、女性の開発者が苦労したエピソードとして、「女性はブレーキペダルを踏むときにカカトを床につけないで踏む人が多いということを男性の開発者たちに伝えても、なかなか理解してもらえませんでした」とコメントしています。
サーキットでのドライビングレッスンなどでは、正しいブレーキペダルの踏み方として、AT車など2ペダルの場合、足をブレーキペダルに対してまっすぐ垂直になるように置きカカトを床につけると教えられます。
そして、足の指の付け根の部分がブレーキペダルの中心にくるようなイメージでブレーキペダルを踏むようにして、アクセルペダルを踏むときには、カカトを床につけたままそこを支点にして、つま先を右に傾けて踏むとどちらもスムーズに操作でき、コントロールがしやすくなるとされています。
ただし、ほとんどのドライバーが最初に運転を教わる自動車教習所では、「ブレーキペダルを踏むときはカカトを床につけない」と教えていることが多いようです。
これは、初めてクルマを運転する人では、まだブレーキペダルをコントロールすることが難しく、ペダルの踏み遅れや踏力不足による危険性を考慮し、まず確実にブレーキを効かせることを優先していることが理由だと考えられます。
年齢を問わず、カカトを床から離してブレーキペダルを踏む女性ドライバーが多いのは、自動車教習所で教わったことを忠実に守って運転していることもあり、力を込めて踏もうとするとカカトが床から離れてしまう人が多いようです。
また、男女の身長差も関係しているといえます。成人男性の平均身長は168cmから172cm程度、足の大きさは26cmから27cm程度ですが、女性の平均身長は154cmから158cm、足の大きさは23cmから24cmと、女性の方が身体のつくりが小さいことも原因となります。
身長が低いと、視界を確保するためにシートを高く上げることになり、足がブレーキペダルに届きにくい状態になってしまいます。
その上、足のサイズも小さいと、カカトを床につけた状態では、つま先のほんの先端がブレーキペダルに触れるくらいになってしまうため、そこからペダルを踏み込もうとするとどうしてもカカトが床から離れてしまうのです。
いずれにしても、カカトを床につけずにブレーキペダルを踏むと、ジワリと少しずつ踏み込んでいくようなコントロールは難しく、踏み始めから強い力が加わってガクンと急ブレーキのような挙動になりがちです。
デイズの開発現場では、カカトを床に付けずにブレーキを踏む女性が多いことを男性の開発者に話すととても驚かれたといいますが、社内の女性たちの声を集めるなどしてなんとか男性陣に理解してもらったそうです。
そしてデイズでは、カカトを床につけずにブレーキを踏んでも、初期制動がなるべく穏やかになるよう、また恐怖感を感じずに着実に減速できるよう、何度も試行錯誤しながらブレーキフィーリングを煮詰めていったほか、足の小さな人でもしっかり踏めるように、ブレーキペダルの角度を研究して採用したとのことでした。
※ ※ ※
カカトを床につけずにブレーキペダルを踏むことが良いか悪いかという議論は、個人的にはナンセンスだと思います。
これは男女の差というよりは、体格の違いや運転技能の差の問題であって、車種によってシートの位置調整機能やペダル配置がそれぞれ違うことも影響してくるので、すべての人に「これが正しい」と当てはめるよりも、まずは確実にブレーキを効かせることの方が重要だと考えるからです。
男性にとっては考えられないような「女性ならではの現実」を考慮し、ミラトコットやデイズのように、開発に活かしてくれるクルマが今後も増えていくことを期待しています。
ーーーーーーーーーーーーーーー ここまで ーーーーーーーーーーーーーーー
——————————————————————————————————————————————
こんにちは Oです。8月のスクールは無理ですがツーデーには参加するつもりで予定を組んでいます。
さてブレーキペダルとかかとの話題がありましたが、別の角度からみたこんな記事がYahooに載っていました。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190821-00168208-kurumans-bus_all
しかし女性がかかとを床につけたがらないのは、体格の問題だけではなく、女性用の
靴はハイヒールではなくてもかかとがかなり高いものが多く、かえって不安定になる
可能性があること、また靴の後ろを傷つける可能性があって、おしゃれで高価な靴
だったりすると嫌がることもあると思います。
また運転教則本ではかかとを離して踏み替えるよう指導されていますが、これは教本
の普通免許対象が乗用車に限らずマイクロバスから軽トラック、小型特殊までを対象
にしていて、床からペダルが生えているような種類のものでも通用する非常に普遍的
なペダルの踏み方を念頭に入れているためだと思います。教本が常に正しくて最適と
いうことにはなりません。